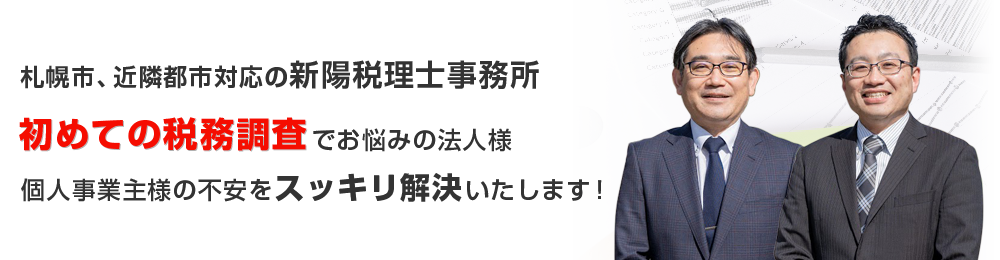税務調査はどのくらいの確率で来る?~実際のデータと傾向~
「うちにも税務調査が来るのでは…」と不安に思う経営者や個人事業主の方は多いと思います。
しかし実際には、税務調査は全員に行われるわけではありません。
税務調査の「確率」「タイミング」「選ばれる理由」について解説します。
1. 税務調査の確率はどのくらい?
国税庁(令和5年度)の資料によると、最近ではコロナの影響もあってか調査件数は減少しています。
実地調査の件数は法人・個人合わせて毎年およそ10万件前後。これを全国の申告件数で割ると、
法人:約1〜2%前後
個人事業者:約0.5〜1%前後
といった確率になります。
つまり、100社あれば毎年1〜2社程度が調査対象になるイメージです。ただしこれは単なる平均で、業種・規模・収益構造によって大きく変わってきます。
たとえば現金取引の多い飲食業や小売業、利益率が高い業種、売上や経費の動きが極端な場合は、比較的調査対象になりやすい傾向があります。
また、税務署も限られた人員で効率的に調査を行う必要があるため、単純な「ランダム抽出」ではなく、データ分析、最近ではAIを用いた選定が行われています。
2. 税務調査が来る「時期」とは?
税務調査が行われる時期には一定のパターンがあります。
基本的には年中調査は行われていますが、特に税務署の繁忙期を避けた春(3月後半~6月)と秋(8月~12月)が調査の多い時期です。
特に秋の税務調査は税務署の事務年度(7月開始)の始まりで時間的余裕もあるため深度の深い調査になる可能性があります。
3. 税務調査に選ばれる主な理由
税務調査は「無作為」ではなく、「理由があって選ばれる」ことがほとんどです。
代表的な選定理由には以下のようなものがあります。
・売上が前年と比較してかなり増加している
例えば3年連続で売上の前年比120%で推移すると、1年目が1億円の売上とすると3年目で1億7,280万円にもなります。
3年でほぼ倍増に近いので、「そろそろ調査に入っておくか・・・」ということにもなりかねません。
・特定の経費の伸び率が高い
例えば、売上は前期と同じくらいなのに、交際費や支払手数料などが前年比200%になってるなどあれば、調査対象になりやすいです。
そもそも、交際費や支払手数料という勘定科目は税務調査でも厳しくみられる項目ですし、重点を絞って調査されることもあり得ます。
・利益率が同業他社と比べて極端に高い・低い
税務署はいろいろな会社のデータを持っています。類似同業者と構成比が違えば、「何かあるのでは・・?」と考えるでしょう。
・現金商売で、売上除外のリスクが高い業種
飲食業、理美容業・小売業など現金取引が多い業種は、時期に関わらず税務署は目を光らせています。
これらの業種は現金管理をきちんとされているかどうかポイントになります。
・赤字が長年続いており、事業継続性に疑問がある
長年赤字だと、「どうやって生活しているのか」「赤字補填の原資はどこから捻出しているのか」という疑問が生じます。
やはり売上除外や経費水増しなどを疑ってきますので、きちんと説明できるようにしておくと良いです。
・主要取引先に税務調査が入った
税務調査ではその会社の調査以外に、「関連業者の資料集め」も行われます。
特に個人事業者の場合は申告の有無を照会することも税務署の重要な仕事の一つです。
・税理士の申告内容に誤りが多く、信頼度が低い
税務署では内部資料として税理士ごとの傾向を把握していると言われています。あまり非違時効が多い税理士事務所だと重点的に調査が入る可能性があります。
また、税理士の情報だけでなく、税務署は各種情報(資料せんや銀行取引情報など)も持っているので、帳簿だけでは分からない不自然な動きをチェックしています。
4. 税務調査の通知と実地の流れ
税務調査の多くは、事前通知がされ調査が行われます。
一番多いケースとして、税務署職員から電話で連絡が入り、「〇月〇日に伺いたいのですがご都合はいかがですか」といった形で日程調整を行います。
通知から実際の調査までは早くて1〜2週間程度、長くて1か月先でしょうか。納税者の個別事情にも柔軟にたいおうしてくれるケースがほとんどです。
原則法人の調査では1〜3日間の実地調査が行われ、帳簿(総勘定元帳・補助元帳)・や書類関係(領収書・請求書・契約書・通帳)などを確認し、正しい申告がされているかチェックされます。
一方で、無予告調査(抜き打ち)で税務署が事前連絡なく突然訪問する場合もあります。
これは、現金商売や、脱税や無申告などの情報を入手している場合、証拠隠滅の恐れがある場合に行われるものです。
5. 税務調査に備えて今できること
税務調査は「突然やってくるもの」ではありますが、日頃の準備によって対応リスクを大きく下げることができます。
具体的には次のような点を意識しておくと安心です。
・帳簿・領収書・契約書を正しく整理・保管しておく
・現金取引や交際費など、説明が求められやすい項目の記録を残す
・売上や経費の根拠資料を明確にしておく
・グレーな処理は、必ず税理士に相談する
税務署は、領収書のある・なしだけを確認するわけではありません。
例えば「その支出をするに至った理由」に疑義があれば、「否認します」「役員賞与にします」など修正を求められることにもなります。
このあたりは日々の税理士とのコミュニケーションによって、税務調査リスクの管理をしておくと良いでしょう。
6. まとめ
税務調査というと「怖い」「不安」というイメージを持たれがちですが、実際には、「正しい申告を確認するため」の調査であって、正しい経理と申告をしていれば心配する必要はありません。
逆に、調査の機会をきっかけに、帳簿管理や会計処理を見直す良いタイミングになることも多いです。
普段から税理士とコミュニケーションをとって、不安な点や判断に迷う取引は早めに相談しておくことが重要です。
このように、普段から正しい経理を行うことで税務調査のリスクは大幅に減らすことができます。
また、税務調査は、普段からの準備と実地調査時の対応次第で結果が大きく変わります。
実際の現場では、税務署との交渉や修正申告の判断など、専門的な対応が求められる場面も少なくありません。
弊所では、法人・個人を問わず多数の税務調査対応を行っており、初めての方にも分かりやすくサポートいたします。